じっくりと考える問題を解いたり、年度の初めに算数アンケートをとると、必ずといってもいいほどこういう回答をする子がクラスに数名います。
「考えるのが、めんどくさい」
もちろんそういった子たちでも授業にはちゃんと問題を解いてはいるし、中には算数が得意な子もいます。それでも心の底にはじわじわと「めんどくさい気持ち」が流れているのでしょう。
でも僕は、この「めんどくさい反応」を起こしている子とかかわるのがわりと好きです。だって、脳みそにとって、そもそも考えることはとてもめんどくさい作業だし、その身体信号に素直だから。
よくよく話を聴いてみると、塾や計算ドリルで徹底的反復練習によって鍛えられている子が多い。算数は「計算を早く、多く解く」ことだと誤解してしまっている。算数・数学の問題は、おまえはもうすでにわかっている問題を北斗百列拳のごとくあたたた解かされたり、はたまた、自分の力量にあっていない問題集を与えられた仕事をただただこなすよう努力する消費型タスク問題となってしまっていることがわかります。ひでぶ!
こういうトレーニングを続けていれば、算数・数学のもつパターンのおもしろさやその世界の広がりには気づけません。もちろん、最低限の計算能力は必要ですが、本当に夢中になってときたい問題と出会えれば、必要感が生まれてドリル問題であっても「ふつう」におつきあいできるようになってくるものです。ぎゅうぎゅう詰め込む必要はありません。ぎゅうぎゅうは焼き肉屋で十分です。既にわかっているのに、ただただ繰り返し出される問題の数々に、考えることをめんどくさいものと思わせてしまった教え手や問題の渡し手のほうに責任があります。
「考えることがめんどくさい」と言っている子たちの中には、問題をスラスラと解答できる子も多くいます。基礎的な知識の抜けが多く、解くことにまだ時間がかかっている子もいます。その子たちだって、算数・数学を好きになる可能性があります。
子どもたちに欠けている経験を補ってあげること。それは、「解きたいな」と思える魅力的で自分にあった問題と出会えること。しかもそれが選択できること。そして、「一緒に考えたい」と思える仲間に出会えること。それらを「数学者の時間」で支えているなと、やってみて改めて思うのです。
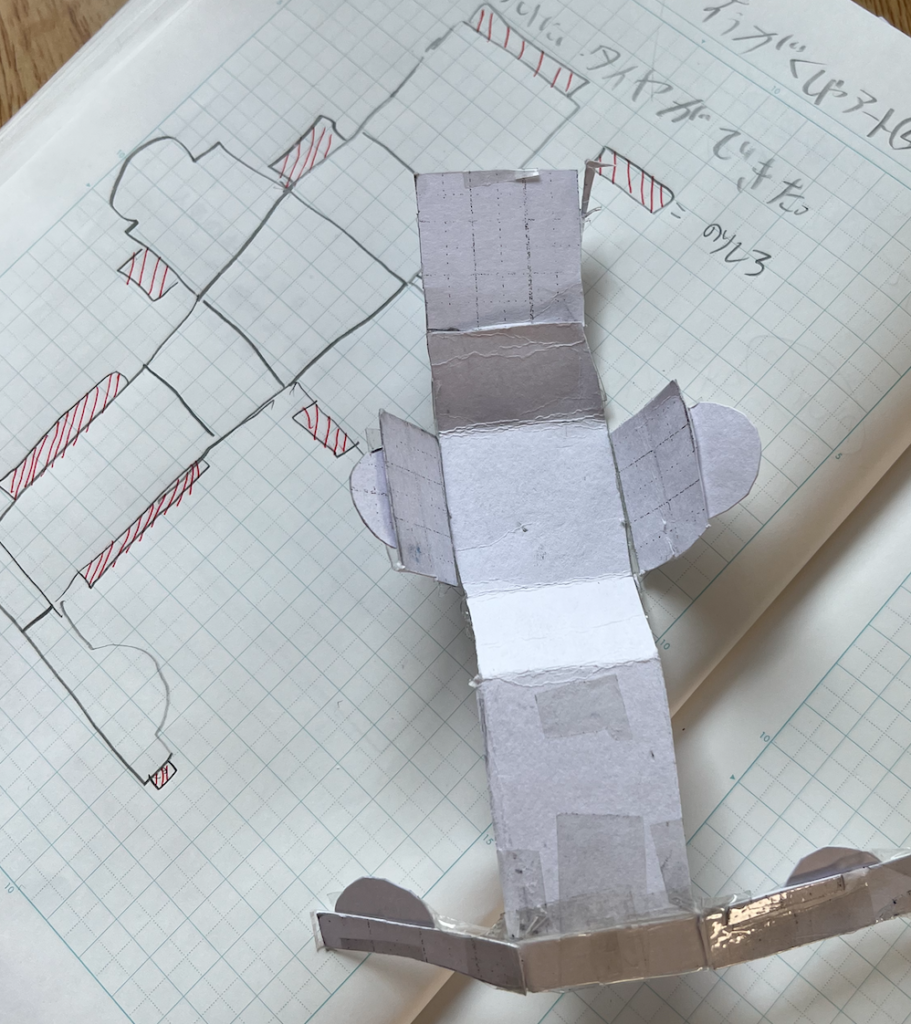
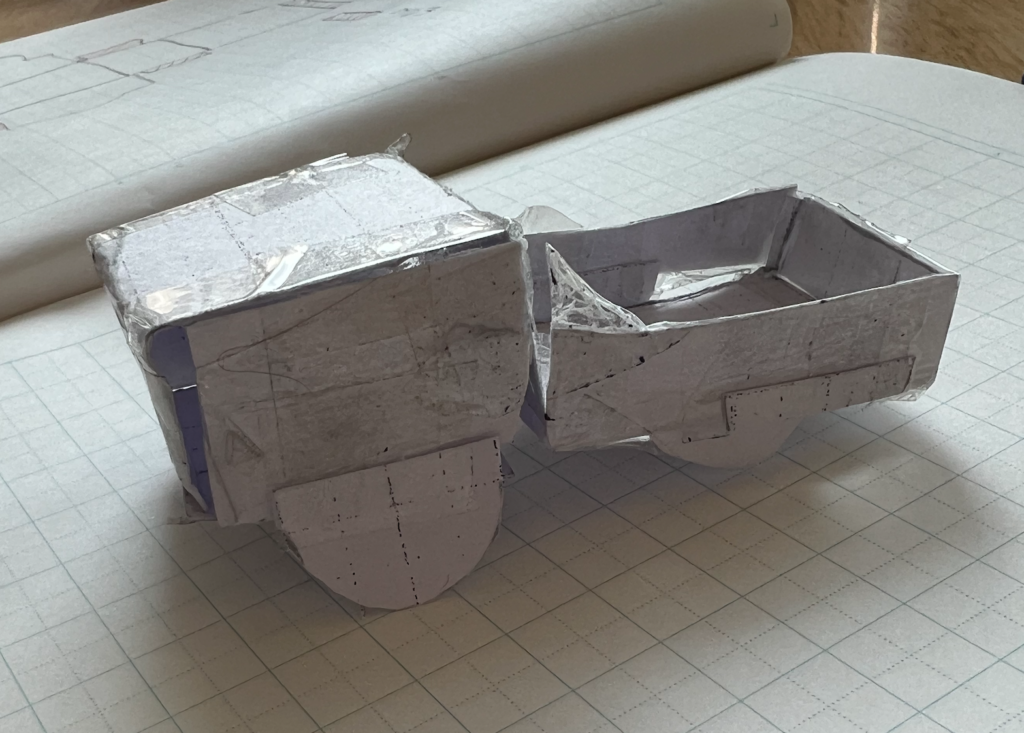
考えることが好きな子は、いつまでもこういうことを繰り返しています。