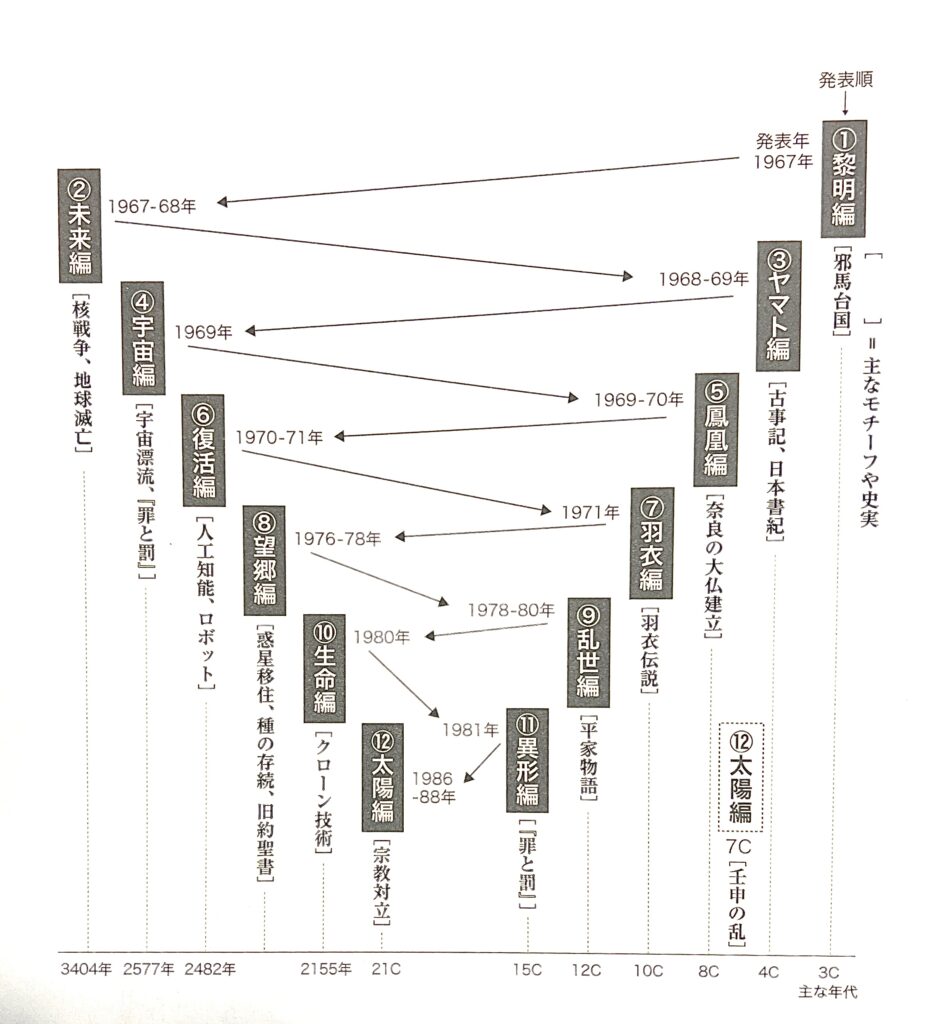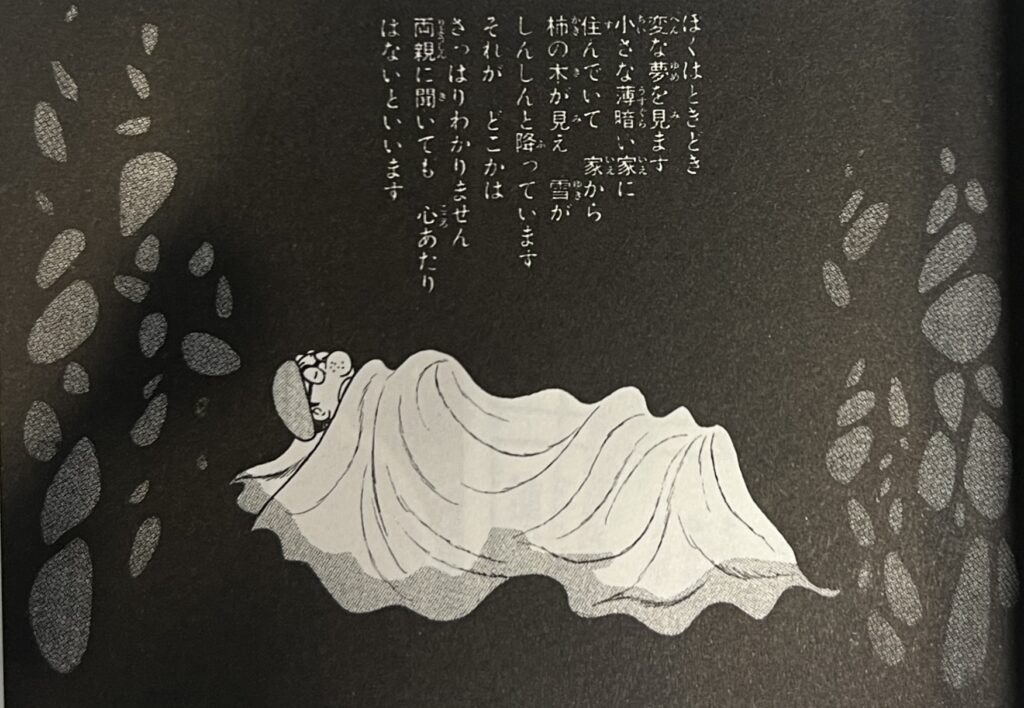東京都内の私立初等学校の教員が集う全体研修会に参加した。会場は成城学園初等部。今回の目的は、秋山さんによる「生成AI」をテーマにした4年生の授業を参観。教室には入りきらないほどの教員が集まり、このテーマへの関心の高さがうかがえた。
教室の子どもたちは私服で、明るく、どこかやんちゃな雰囲気。先生が何度も声をかけて落ち着かせようとする姿に「ああ、やっぱり学校だ」と思わず頬がゆるむ。成城学園では一人一台のiPadが整備され、ICT先進校としての環境が整っている。僕自身も日々の仕事で生成AIを活用しており、今回はAIと子どもたちの出会いがどのようなものになるのかを楽しみにしていた。
相談するのは生成AI、それとも友だちか?
授業は「生成AIとは何か」という昨年度の学習のふりかえりから始まった。
「AIって、組み立て工場みたいなもの」
「パズルの結果を示してくれるもの」
という子どもたちの含蓄ぶかい回答に、思わず「なるほど〜」ときいていた。
今回の授業で投げかけられた問いは、友だちとケンカしたとき、生成AI(学校AI「つばここ」)に相談することについてであった。これは今後、子どものたち中に、どうAIを使っていくかの判断基準をつくるきっかけとなるよい切り口だと思う。うなずきながら子どもたちの意見をきいていた。
「つばここに相談すると、なんでも聴いてくれるから気持ちが軽くなる」
「友だちは、ケンカもするけど、ちゃんと話をきいてくれる」
「友だちは、(私のことを)思い出してくれる」
中でも、いいなと思う意見に
「友だちとは思い出ができる」とあった。
子どもにとって思い出とは、情報のやりとりではなく、生身の体験なんだと想像しながらきくことができた。
そして、「友だちはデータをまとめるのがおそい」「けどAIは解答が長すぎる、一文でほしいのに」など笑いを誘っていた。
最後に、先生からAIを利用する際の、ゆさぶりをかける授業の仕掛けがあった。子どもたちはAIに触れる経験よりも、大人や友だちに相談する経験のほうが豊かなため、人間を選ぶ意見が大半だったが、この問いを通して、AIを子どもが使うことについて考えるきっかけとなっていた。
この思い出となる生身の体験だったり、データを処理するためのスピードだったり、AIを捉え直す際の、考えたくなるおもしろい視点を子どもたちは提供してくれている。
授業にAIを導入する際の、入り口の授業づくりとして子どもたちがよく考えたくなる授業設計が秀逸だった。先生は本当はもっと時間がほしく、一人ひとりの子どもたちが何を感じ、考えたのか、意見を交換しながら議論をじっくりとすすめることをしたかったと思う。
AIは内省を助けるの?
さて、生成AIを子どもが使うことによって考え起きたい問題とは、いったい何だろう。最近、子どもたちと接していて強く感じるのは、「自分の中にもう一人の自分を持つこと」の難しさがあげられる。
「私の中に他者がいる」という感覚を育むには、心理的な安心感を土台に、ひとりで考える時間、つまり孤独と向き合う力が必要だ。今の子どもたちは常に誰かとつながれる環境に生きている。SNSによって孤立の時間が奪われ、同様にAIも「ひとりでいること」を許さなくなってしまうのではないだろうか。僕自身、SNSが時間を奪い、内省を妨げる装置であることを日々反省。
安易にAIを利用することは、内省するための言葉の豊かさを失っているのではないだろうか。そこでは「だるい」「うざい」といった単純な言葉に回収されてしまい、言語化されないモヤモヤした感情に向き合う度量が希薄になってしまっているのではないだろうか。こうした感情に向き合うためにAIに相談するという行為は、果たしてどういう意味をもつのだろうか。
自分の内側にある、まだ言葉になっていない思いを、スクリプトに代替させてしまったとき、それは果たして「自分の言葉」といえるのだろうか。それは本当に、自分を癒すものとなるのだろうか。生成AIは、あくまで「言語化された問い」と「言語化された応答」の枠の中でしか動けない。そこで起きるのは、内省ではなく、反応の繰り返しだ。
AIの前で「とりあえず何かを聞いてみる」という姿勢が習慣化すると、自己との対話は「AIに操作される対話」になりかねない。そして、すぐに応答を得ることの快適さに慣れると、「考え続ける」ことへの耐性が弱まっていく懸念もある。
子どもたちには、答えの出ないモヤモヤを抱え続ける力を育てたい。そのモヤモヤをどう言葉にしていくか、その道のりこそが内省であり、その道をAIにどこまで委ねてよいのか。今、立ち止まって考えたい。
よりよいアイディアは、まねるといいの?
AIから提示された「よりよいアイディア」が、常に価値があるとされるようになったとき、子どもたち自身が生み出す素朴なアイディアの価値は、どのように見なされるのだろう。
先週、夏祭りのお化け屋敷の企画を考えていたときのこと。ある子が、中学校の文化祭で体験した「事前に怖い動画を見てから入る」仕掛けを提案した。それに対し、普段はふざけてばかりの子が言った。
「僕はそれをまねしたくない。自分たちで考えたい。オリジナリティーでしょ」
でも委員会の空気はその動画アイディアに傾き、その子も結局は「やっぱりそれがいいや。おれやりたい」と気持ちを翻した。このやりとりを見ていた僕自身は「本当にこれでよかったのだろうか」と、何だかざらついた気持ちが残ってしまった。誰が言うかよりもアイディアそのものの高さを問われているような気がした。安易によいアイディアに真似しすぎてしないのか。もう少し捉え直しが必要だと思った。
教育で育てたいもの
AIが持ち込む価値観は、「効率」や「役に立つかどうか」といった生産性がある。一方、教育が本来育てようとするものは、「違和感を手放さない感性」や「その人の文脈への理解」のはずである。
あえて「誰が言ったのか」に耳を澄ませる文化がなければ、民主的な教育にはならない。アイディアの高さではなく、「そのアイディアを言った人の背景・関係・立場」に注目する中動態的な視点が必要だ。
もちろん、まねることは悪いことではない。世阿弥の『風姿花伝』にある「守・破・離」が示すように、学びはまず“まねる”ことから始まる。しかし、それを自分の技にするには、そこに術者自身の意図と反復が必要である(風姿花伝を紐解いた西平直『稽古の思想』に詳しい)。
自分の技として身に付けていくためには、繰り返しとその練度がためされる。その際、まねようとする術者の意図があってこそだ。AIを使うことで、この意図が離れ、アイディアが「いいことおもいついた!」とひらめくことへの素地を失ってしまわないだおろうか。それとも、AIが提示するより精錬されたアイディアに魅力を感じるのだろうか。これは自戒も込めて考えていきたい問い。
AIとの関わり方をどう設計するか
AIを子どもがどう使うかという問いは、教育者が子どもにどんな社会をつくってほしいか、どんな人間になってほしいかという願いと結びついている。AIをつかった授業の先にみたい景色ってなんだろう。
AIが持ち込むのは、「役に立つか」「効率がいいか」といった生産性の価値観。教育で育てたいのは、生産性ではなく、「問うこと」や「違和感を手放さない感性」だったりする。アイディアは、単なる結果ではなく、その人がどう見たか・どう考えたか、わかろうとしなければ、見えなくなる。人と一緒に生きていこうとするため、その人の背景を理解しようとする感度を、失敗しながら身に付けていくその体験そのものはすっとばせないから。
「AIの導入はバランスよく」とい言いたくなるが、現場の中で具体的にどう扱うか、その設計者の哲学が問われている。避けては通れないAIの時代において、思考停止せず、もう少し考えていこうと思う。
この授業は、そんな思考を促してくれる刺激的な時間であった。僕の勤務校は「ICTをあえて使わない」という逆張りの方針をとっているが、子どもたちの日常にはすでにAIが自然に入り込んでいる。近い将来、僕自身も子どもたちとAIについてじっくりと語り合う時間をつくりたい。
現在、国語の授業では今井むつみ氏の『AIにはない「思考力」の身につけ方』(ちくまQブックス)を子どもたちと読んでいる。行事の合間を縫うような進行であり遅々として進まないが、いずれ再び哲学対話のような時間を持ち、「自分はどうありたいのか」をともに考えていきたい。
会場で久しぶりに再会した、まーしーの第一声がウケた。
「ベンチプレス100キロ、おめでとうございます」
そっちか!と思わず笑ってしまった。