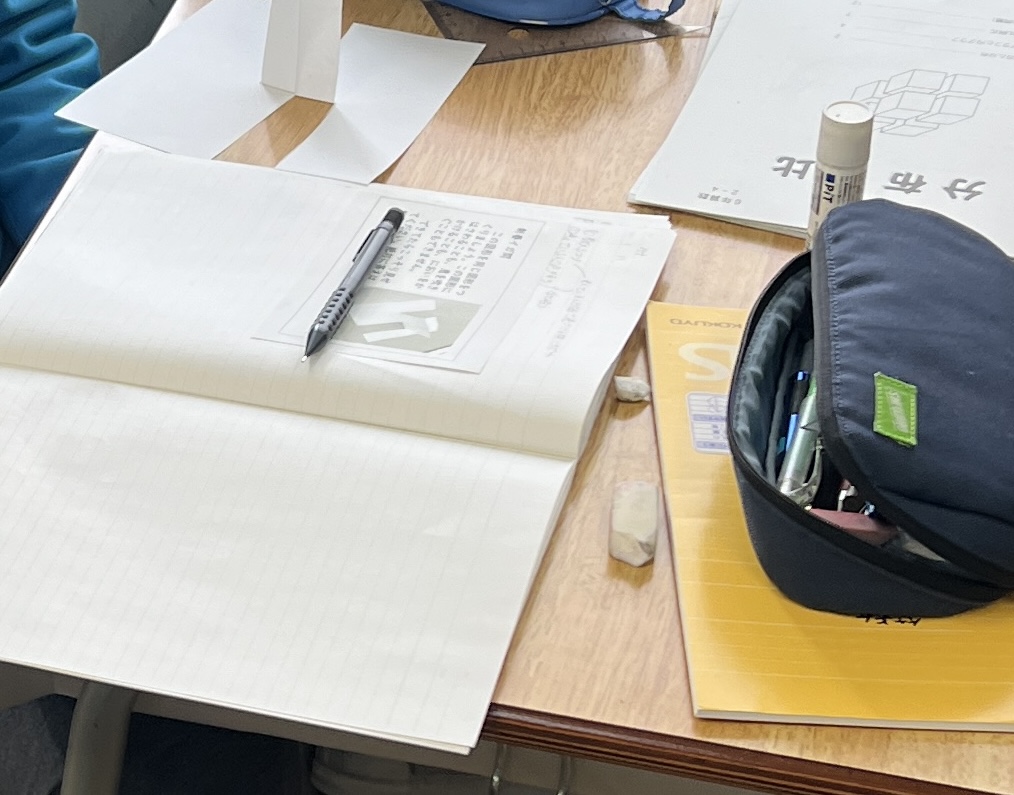3学期の授業がはじまった。算数1発目の授業びらきは、先日の合宿で経験したファシリテータートレーニングからはじめてみた。
“ファシリテーターはまず「みる」から。けど、どうやったら「みる」ことができるの?” 2024/01/05
「頭の目かくしをとる」問題をあつかいつつ、「学び合う質の向上」をめざした。
僕は、子どもたち同士の「学び合い」では、よく「教え込み」が起こることをずっと懸念していた。会話を聞いていると
「ここはこうするでしょ。ほら、できたでしょ」
みたいなやり方をよくレクチャーしている。これでは、学習者は何も考えないで、アドバイスをくれる友だちと待ってしまう。ヒントをこっそりと期待してしまう。
そこで、先日のLAFT合宿で経験したKAIが提案した「不可能な立体」づくりを問題を扱ってみた。考えることに加え、自分の「学び合い」のプロセスをメタ認知する練習をしたいと思ったからだ。
「この答え、わかった人は、絶対に教えてはいけません。もちろん、ヒントもダメです。でも、相談には乗ってあげてください。じゃ、がんばって」
頭のやわらかい子は発想を転換して、すぐに問題を解けてしまう子もいた。
「この問題、TikTokでみたことある!」といっていた子は、ただ見たこと有る様だけなので、解けるまでかなりの時間を要していた。見たことあるだけではわからないのは世の常だ。
「何をしているかずっと(友だち)を見ているけど、ついヒントを教えたくなってしまう」
「どこを切っているのかを見ていたけど、どこまで言っていいのか難しかった。できそうだったらヒントを言いたくなっちゃう」
「まちがっていた人にどうしても答えを言いたくなりました。教えることもとても頭を使う」
答えが分かった子は「教えたくてむずむずする」ようだった。「教える方が解くより数倍難しかった」と。
一方で、相談にのってもらっている子達の気持ちも聞いてみた。
「まわりがみんな簡単に解いちゃうから焦った」
「できるようになりたい」「教わりたい」という子も一定数いるようだったが、別の意見が出てきた。
「自分でひらめけてすごい嬉しかった。嬉しくて分かった分かった!って叫んじゃった」
やっぱり、自分でひらめきたいし、答えまでたどり着きたい。
だからヒントは極力いらないと。
考えている人を尊重しようと、そこでまず「みる」「きく」ことから相談者ははじめることとなった。
相談に乗ってくれている人は
「ヒントを出すと、いい気持ちになる」
と共有してくれた。ドッと笑いが起きたが、これ真実だろう。常に、人より優れていたいと表す心模様なのかも。
学び合いをしているようで、じつはたくさんの教え込みにあることを気付いた。
子どもたちとは、僕が相談しているときに使っているツールをプレゼントした。
①「今、どんなかんじ?」(現状の確認)
②「どうしたいの?」(本人のゴールの確認)
③「こういうのはどう?」(現状とゴールのギャップを埋める提案、ここではじめてヒントがでてくる)
「あ、イガせんのいつものやつね」
「つかえそうじゃん!」
少しずつ、また教え合いの質が変わっていけるといいなと思う。
最後まで、解けない子もいたけど、次の理科の時間にずっとこっそり手を動かして、やっとできて嬉しかったと教えてくれた。
自分で考えたいなって思える子、いいなと思う。そういう授業をつくっていきたい。