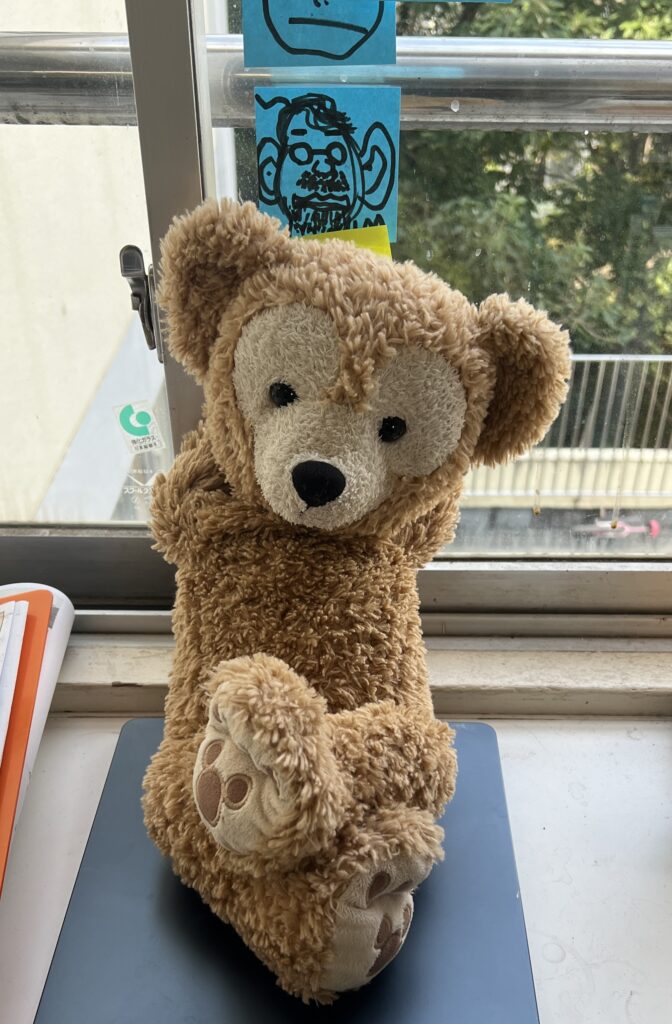LAFTの次のシーズンテーマは「概念型探究」に決めた。そのキックオフとして、秋吉梨惠子さんに「概念型探求のはじめの一歩」という話をしてもらった。その中で印象に残ったのは、「いずれにしても、概念型探究に取り組むには、自分が何をやりたいのかが大事」という言葉だった。
学校で何かを実践するには、当然ながらカリキュラムの枠がある。公立にも私立にもそれぞれの制約や文化があり、教えられる内容や方法には幅がある。だが、その中で何を子どもたちに伝えたいのか、自分はどんな学びを願っているのか、そこを見つけることが出発点になる。その言葉は、「本当に自分がやりたいことを見つけていかなければ、概念型探究も続かない」というメッセージとして響いた。
つまり概念型探究を支えるのは、教師自身の自分の探究かもしれない。教科の概念を深めようとすることと、自分の教師としてのあり方や信念を見つめ直すこと、実は地続きの営みなのだと思う。
振り返ってみれば、僕自身もまさにそうだった。この十年は「数学者の時間」実践に軸足を置き、そこにさまざまな学びをリンクさせてきた。それができたことはとても幸運なことだったと思う。けれど、ここにたどり着くまでには多くの試行錯誤があったのも事実。
20代、30代のころの僕は、決められた公立学校の枠の中でいかに自分の思う「より良いもの」を形にするかにこだわっていた。反骨心を燃やし、時には自分を保留し、うまく人と折り合いながら、自分の立場を確立しようと必死だった。
一方で、今の学校現場は、状況そのものがかつてよりもずっと厳しい。忙しさのあまり、教師同士で語り合う時間や、外へ学びに出かける機会が極端に減ってしまっている。そんな中で、あえて立ち止まり、自分の内側を見つめ直す時間を持つことが難しくなっている。本当は、こういう自分自身の実存と教師とのつながりを見つけることこそ、大事なのに。
けれど、だからこそ、外の風に当たることが必要だ。やってみたいことや「もう少し深く知りたい」と思うことを調べたり、本を読んだり、学びの場に身を置いたり、そんなチャレンジが、自分の原点を見つけるための第一歩になるはずだと思う。
僕がこれまで自分の「やってみたいこと」を見つけてこられたのは、やはり人との関わりのおかげだ。教育相談室で、まだ右も左もわからない僕をまるごと受け止めてくれた木津先生だった。東京教師塾で、徹底してやり抜く力を教えてくださった原田隆史先生と塾生たち。夜7時に始まり朝5時に終わる勉強会、あの場には唯一無二の熱量があったし、今の自分を逸れ抜きには語れない。
その後、ゴリやKAIと共に、PA(プロジェクト・アドベンチャー)やワークショップ授業に触れ、仲間とともに実践を深めていく面白さを知った。吉田新一郎さんとの出会いも、自分にとっては大きな転機で、学校というフレームを相対化し、自分の立っている場所を新たな視点から見つめ直すことができた。そして今も、LAFTや職場の同僚たちと刺激し合いながら、新しい学びを共につむいでいる。
思えば、僕が「教えたいことのこだわり」を持ち続けてこられたのは、何かの本で学んだからでも、研究の成果だけでは決してない。人との関係ややりとりの中で、触発され、自分が育てられてきたからだ。ひとりでは決して辿りつけなかった場所に、誰かとの縁が導いてくれたんだとおもう。
「自分のやりたいことがわからない」と感じている人がいるのなら、ぜひ外へ出て、誰かと語り合ってみてほしい。職場の外の学びの場に身を置き、他の教師や研究者、様々な人たちと関わってみてほしい。その中に、きっと自分の心を動かす何かがあるはず。
教師としてやりたいことは、最初から見つかるものではない。人とのつながりや響き合いの中で、少しずつ形づくっていけるもの。学校の先生として生きることは、関わりの中で自分自身を更新し続けることなんだとおもう。